|
|
|
Keiworksのクラッチケーブルが切れたので、修理/交換します。
|
| ★今回取付する商品の紹介 |
|
・SUZUKI純正部品 ケーブルアッシ,クラッチ [23710-75H00]
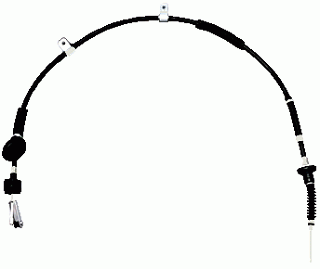 【詳細】 【詳細】
|
・品番
・部品製造年月日
・適合車種
・購入金額 |
23710-75H00
2016.11.25.
Kei[HN22S]、アルト[HA12S HA23S]、ラパン[HE21S]、ツイン[EC22S]
\3,348 (税込[8%]) SUZUKIディーラーで購入。※購入時の価格と消費税率です。
※社外品\2,570〜 (税込[8%])で販売されています。 |
 関連:車の部品購入時に車検証で確認する事 関連:車の部品購入時に車検証で確認する事
→ こちら
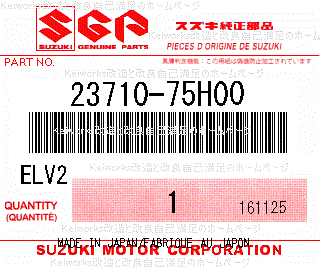
|
|
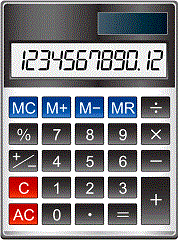 ●クラッチケーブル交換の作業時間と費用について ●クラッチケーブル交換の作業時間と費用について
・SUZUKIの標準作業時間は「0.7」で約40分です。
作業環境の整っていて、作業になれた方の時間だと思います。
・工賃は下記のようになります。 ※ページ作成時の金額です。修理依頼する所に確認してください。
ディーラー → \6,048〜(税込[8%])
整備工場など → \4,536〜(税込[8%])
純正部品と工賃の合計は下記のようになります。
ディーラー → \9,396〜(税込[8%])
整備工場など → \7,884〜(税込[8%]) |
| |
| ★クラッチケーブル切断について |
|
【クラッチの切断する症状について】
・クラッチケーブルが切断する前にいくつか信号みたいなものがあります。
クラッチペダルを踏んだ時に重くなる。(だんだん重さが増してくる) → グリスアップをしていましたが、症状改善できませんでした。
クラッチペダルを踏んだ時に異音が出る時がある。
ギヤが入りにくくなる。(特にリバース)
の3つが私が身をもって感じたところです。
また、クラッチペダルを踏んだ時に重くなっている状態で運転すると、左足がツル時がありました。
その時点でクラッチケーブルを交換していればよかったです。
通常は25,000Km目安と言われていますが、この時の走行距離が141,100Km以上走行しているので寿命でした。
【クラッチケーブルが切断した後】
・クラッチケーブルが切れる時は突然「バツ」って大きな音がします。
・クラッチケーブルが切断したら車を安全な場所に停車させてください。
路上に停める場合は、ハザードと三角表示板、場合によっては非常信号灯を使います。
夜間に車を押して移動させたりするのは非常に危険です。
 関連:エーモン 非常信号灯 関連:エーモン 非常信号灯
→ こちら
このページをご覧になっている方は、車の中に「三角表示板」「牽引ロープ」「ブースターケーブル」は積んでいますか?
私の場合はこの他に、パンク修理剤も積んでいます。
・クラッチケーブルが切れた後は自走は無理なので、ディーラーや自動車整備工場に車の引き取り依頼します。
携帯電話(スマホ)の電話帳に近くの整備工場、ディーラー、JAF、地元のレッカー会社の電話番号は登録した方がいいでしょう。
エンジンの回転を合わせて強引にギヤを入れて移動する事は最終手段ですが、ミッションまで壊すと修理費が膨れるので、この方法はあくまでもどうにもならない時だけです。
それ以外は、車を自走せずに車の引き取りを待ちましょう。 |
| | |
| ★必要な部品/材料 |
★必要な工具 |
|
・つなぎ ※汚れてもいい服装
・作業用手袋
・ティッシュペーパー
・ウエス
・グリス か モリブデングリス
・パーツクリーナー
・針金 ※強度がある物 → 私はワイパーゴムに付いている金具を使用
|
・+ドライバー(#2)
・ラチェットハンドル
・エクステンションバー(長めの物) → 私はスピンナハンドル[300mm]使用
・ソケット[10mm]
・ソケット[12mm]
・スパナー[14mm]
・スパナー[8mm]
・プライヤー
・油圧ジャッキ(3t) ※車載工具可
・リジットラック または コンクリートブロック
・タイヤ止め
・作業用照明 → なければ作業はできません。
・スケール(ものさし) または ノギス → 長さを測れれば何でもいいです。
・鏡 → 作業であれば一番いいです。割れてもいいような物。
|
| ★施工 |
|
 施工時の注意点 施工時の注意点
・整備資格を持たずに施工する場合や、このページを見て施工した場合は、自己責任でお願いします。
・作業は必ず平らな所で作業してください。
・必ず部品を触る前や施工前に、体の静電気を車体以外の金属に触れて放電してください。
・火傷するので必ずエンジンが冷えている時に交換作業してください。 |
| ■エンジン側 クラッチケーブル取外 |
|
 【ジャッキアップ】 【ジャッキアップ】
・パーキングブレーキ(サイドブレーキ)をかけます。
リアタイヤの後ろ側にタイヤ止めをします。
・フロント側を3t(2t)ジャッキで車体を持ち上げます。
・左右の前輪タイヤの横にコンクリートブロックを置きます。 ※リジットラックの代替品
・タイヤの接地位置にコンクリートブロックを置いて、確認後3t(2t)ジャッキをおろします。
・タイヤがしっかりコンクリートブロックに載っているか確認します。 |
|
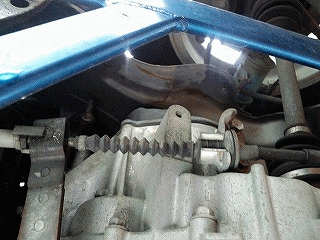 【作業前に】 【作業前に】
・私の車には「Cusco ロアアームバー Ver.2 [612477A]」が取付されています。
エンジン下周りの修理/点検する時は、Cusco ロアアームバー Ver.2取外して作業した方が効率よくなります。
スペース的になんとか作業できるので、今回は取付された状態で作業します。
Cusco ロアアームバー Ver.2を取付されている方で取外して作業する方は、下記の関連リンクを見てください。
 関連:Cusco ロアアームバー Ver.2 関連:Cusco ロアアームバー Ver.2
→ こちら |
|
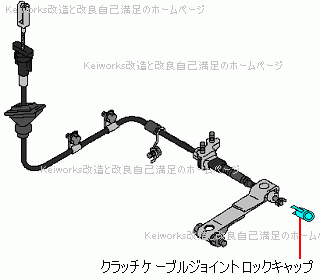 【クラッチケーブルジョイントロックキャップ取外】 【クラッチケーブルジョイントロックキャップ取外】
・エンジン側のクラッチケーブルの先端に付いている白いプラスチックの部品「クラッチケーブルジョイントロックキャップ」を取外します。
このクラッチケーブルジョイントロックキャップは、ナットを固定し回転を防止する役目があります。
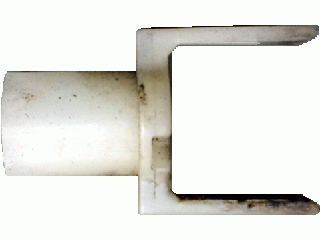 |
|
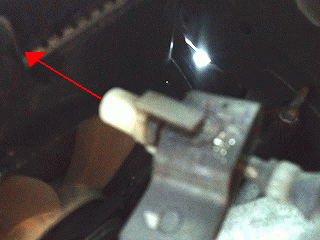 ・クラッチケーブルジョイントロックキャップは、前に引っ張ると取外できます。 ・クラッチケーブルジョイントロックキャップは、前に引っ張ると取外できます。
・クラッチケーブルジョイントロックキャップを取外した後、パーツクリーナーで汚れを落とします。
クラッチケーブルジョイントロックキャップが破損、または無くなっている時は注文してください。
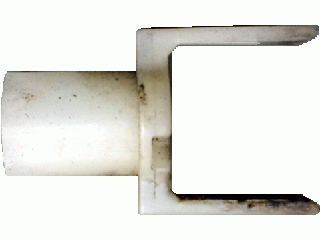 キャップ,クラッチケーブルジョイントロック → 22922-76G00 ※10型 キャップ,クラッチケーブルジョイントロック → 22922-76G00 ※10型
RCテクニカからも「クラッチワイヤー調整ダイアルロックピン」として販売されています。
純正品の販売価格はわからないですが、RCテクニカは\1,026 (税込[8%])で販売しています。
写真を見る限りではどう見ても純正部品です。
|
|
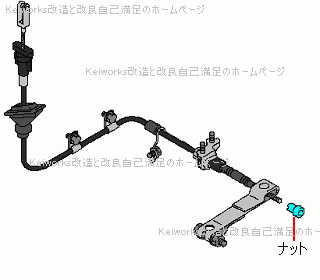 【ナット取外】 【ナット取外】
・クラッチケーブルジョイントロックキャップを取外すとナットが見えます。
このナットはナットの先が湾曲している特殊な形状しています。
このナットでクラッチの繋がりを調整しています。

|
|
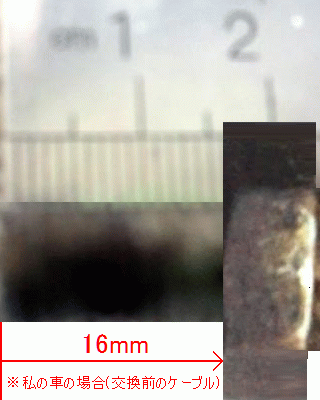 ・ナットを取外前にクラッチケーブルの先端からナットまでの長さを測ります。 ・ナットを取外前にクラッチケーブルの先端からナットまでの長さを測ります。
クラッチの調整時の基準とします。
私の車の場合は16mmでした。 → ※車によって数値は違います。
|
|
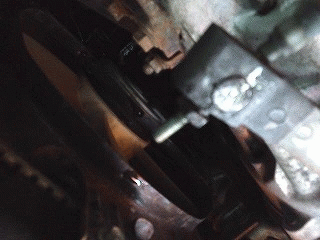 ・ナットをスパナー[14mm]で緩めてから手で回してクラッチケーブルから取外します。 ・ナットをスパナー[14mm]で緩めてから手で回してクラッチケーブルから取外します。
・取外したナットをパーツクリーナーで洗浄します。
このナットの摩耗する部分がひどく削れている場合は、新しいナットを購入してください。
 ナット → 09150-06014 ※10型 ナット → 09150-06014 ※10型
|
|
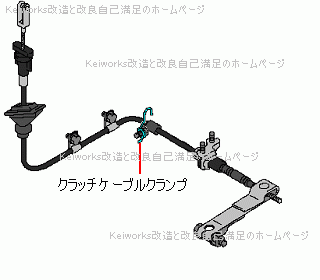 【クラッチケーブルクランプ取外】 【クラッチケーブルクランプ取外】
・クラッチケーブルを取外前に、必ずクラッチケーブルがどの経路で通っていたか必ず覚えておいてください。 |
|
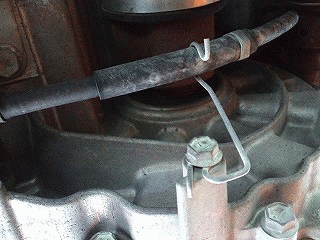 ・クラッチケーブルはクラッチケーブルクランプに挟めて固定しているだけなので、クラッチケーブルクランプを手で押さえてからクラッチケーブルを下に引っ張ると簡単に取外できます。 ・クラッチケーブルはクラッチケーブルクランプに挟めて固定しているだけなので、クラッチケーブルクランプを手で押さえてからクラッチケーブルを下に引っ張ると簡単に取外できます。
(左の写真:左側がフロントバンパー側) |
|
 ・クラッチケーブル取外後です。 ・クラッチケーブル取外後です。
|
|
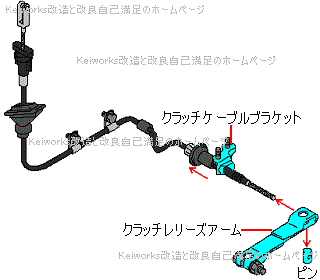 【クラッチケーブルブランケット/クラッチレリーズアーム/ピン取外】 【クラッチケーブルブランケット/クラッチレリーズアーム/ピン取外】
・クラッチケーブルブランケットとクラッチレリーズアーム、ピンからクラッチケーブルを取外します。 |
|
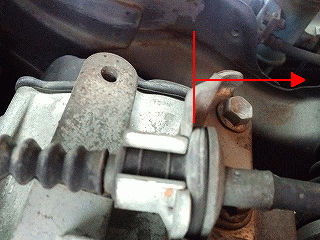 ・クラッチケーブルを車内側へ引っ張るとクラッチケーブルブランケットから取外できます。 ・クラッチケーブルを車内側へ引っ張るとクラッチケーブルブランケットから取外できます。
クラッチケーブルブランケットからクラッチケーブルを取外すと、クラッチレリーズアームとピンも一緒に取外すことができます。
(左の写真:左側がフロントバンパー側) |
|
 ・クラッチケーブルを取外後のクラッチケーブルブランケットです。 ・クラッチケーブルを取外後のクラッチケーブルブランケットです。
(左の写真:上側はフロントバンパー側) |
 |
・クラッチレリーズアームはエンジンに固定したままにして、ピンだけ取外します。
・ピンとクラッチレリーズアームをパーツクリーナーで汚れを落とします。
ピンとクラッチレリーズアームが摩耗しているようであれば新しい物と交換します。
クラッチレリーズアームも折れた場合も走行不能になります。
ピン → 09209-13018 ※10型
アームアッシ,クラッチレリーズ → 23250-73B10 ※10型 | |
|
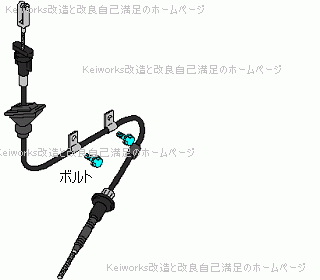 【車体側クラッチケーブル固定ボルト取外】 【車体側クラッチケーブル固定ボルト取外】
・車体側にクラッチケーブルを固定しているボルト(2本)を取外します。
どちらも手の入りにくい所にあります。 |
|
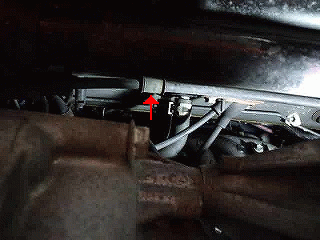 ・助手席側のクラッチケーブルを固定しているボルトは、エバポレータ(車内)に繋がっている黒い配管の近くにあります。 ・助手席側のクラッチケーブルを固定しているボルトは、エバポレータ(車内)に繋がっている黒い配管の近くにあります。
(左の写真:下側はエンジン)
固定しているボルトは、ラチェットハンドルとソケット[10mm]で取外します。
私の車の場合は「Cusco ロアアームバー Ver.2 [612477A]」が取付されているので、近くから手を入れられないので、取外にちょっと苦労しました。 |
|
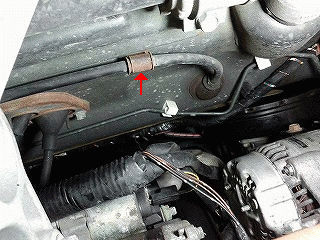 ・運転席側のクラッチケーブルを固定しているボルトは、ジェネレーターの近くにあります。 ・運転席側のクラッチケーブルを固定しているボルトは、ジェネレーターの近くにあります。
(左の写真:下側はエンジン)
固定しているボルトは、ラチェットハンドルとソケット[10mm]で取外します。 |
|
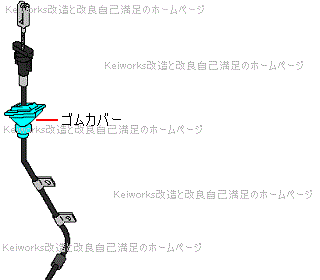 【ゴムカバー取外】 【ゴムカバー取外】
・エンジンルームから車内へクラッチケーブルを引き込む所に黒いゴムカバーがあります。
このゴムカバーを取外します。 |
|
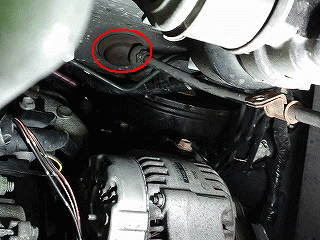 ・黒いゴムカバーはオルタネーターの前にあります。 ・黒いゴムカバーはオルタネーターの前にあります。
(左の写真:写真下側はエンジン)
この黒いゴムカバーは、指で車体下の方に引っ張るだけで簡単に取外す事ができます。
 関連:オルタネーター交換 関連:オルタネーター交換
→ こちら |
|
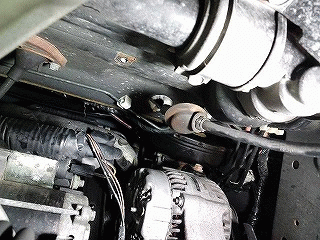 ・ゴムカバーが外れると写真のような状態になります。 ・ゴムカバーが外れると写真のような状態になります。
(左の写真:写真下側はエンジン) |
| |
| ■コンソールアンダートレイ/ダッシュサイドトリム取外 |
|
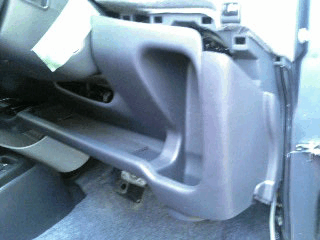 【コンソールアンダートレイ/ダッシュサイドトリム取外】 【コンソールアンダートレイ/ダッシュサイドトリム取外】
・作業しやすいようにコンソールアンダートレイとダッシュサイドトリムを取外します。
コンソールアンダートレイとダッシュサイドトリムの取外方法は、下記の関連リンクを見てください。
 関連:コンソールアンダートレイ/ダッシュサイドトリム脱着方法 関連:コンソールアンダートレイ/ダッシュサイドトリム脱着方法
→ こちら(取外方法)
|
| |
| ■運転席側シート取外 ※運転席側シートを取外して作業する方だけ |
|
 【センターコンソール/運転席シート取外】 【センターコンソール/運転席シート取外】
・作業しやすいよう運転席シートを取外します。
私は運転席シート下にオーディオ用の電源ユニットがあり、取外すことができないので、運転席シートを取外さずに作業します。
運転席シートを取外して作業される方は、下記の手順で取外してください。 |

・センターコンソールを取外します。
取外方法は下記の関連リンクを見てください。
 関連:センターコンソール脱着方法 関連:センターコンソール脱着方法
→ こちら(取外方法)
 関連:サイドブレーキ調整方法 関連:サイドブレーキ調整方法
→ こちら |
|
 ・運転席シートレールに、運転席シートを固定しているボルトを隠しているグレーのプラスチックカバーを3つを上に持ち上げて取外します。 ・運転席シートレールに、運転席シートを固定しているボルトを隠しているグレーのプラスチックカバーを3つを上に持ち上げて取外します。
*ドア側(前)のフロントアウトサイドカバー
*センターコンソール側(後)のリヤインサイドライトカバー(左の写真)
*ドア側(後)のリヤアウトサイドカバー |
|
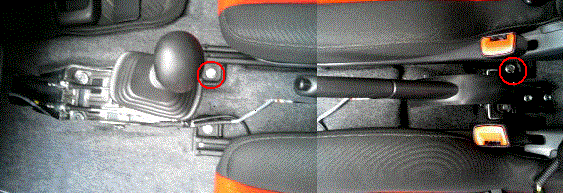 ・運転席シートを固定しているボルト4本を取外します。 ・運転席シートを固定しているボルト4本を取外します。
センターコンソール側のボルトの位置は左の写真の赤丸です。※写真は納車時の頃のものです。
・運転席シート下のカプラー(シートベルト警告灯/シートヒーター[4WDのみ])を取外します。
・運転席シートを車内から取外します。 |
| |
| ■車内側クラッチケーブル取外 ※運転席側シートを取外さないで作業する方は、ここからの作業です。 |
| 運転席シートを取外さずに作業される方は、無理な姿勢で狭い所作業するので、首と背中、腕が痛くなるのを覚悟してください。 |
|
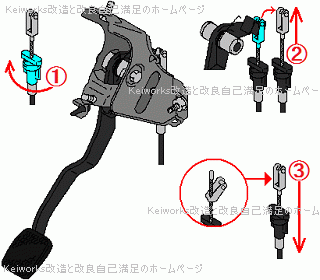 【クラッチペダルからクラッチケーブル取外】 【クラッチペダルからクラッチケーブル取外】
・クラッチペダル上部に引っかけてあるクラッチケーブルの先端を取外します。
作業手順としては左の図のようになります。 |
|
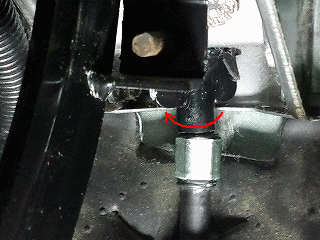 ・クラッチペダルの下奥から出ているクラッチケーブルに付いている黒いプラスチックを90°回すと、車内側でクラッチケーブルを固定しているクラッチペダルブラケットから外れます。 ・クラッチペダルの下奥から出ているクラッチケーブルに付いている黒いプラスチックを90°回すと、車内側でクラッチケーブルを固定しているクラッチペダルブラケットから外れます。
※左右どちらに回しても同じです。 |
|
 ・クラッチケーブルの先端は、クラッチペダルの上部に引っかかっている状態です。 ・クラッチケーブルの先端は、クラッチペダルの上部に引っかかっている状態です。
クラッチケーブルの先端は遊びができているため、ワイヤーを持ち上げただけではクラッチペダルから簡単に取外ができません。
何回かワイヤー部分を上下に動かすと外れます。
知恵の輪を外しているような状態で、ただでさえ体を入れにくい所なのでちょっとイラってきます。
取外時は針金を使用しませんでしたが、針金の先を上手に使うと簡単に外れたと思います。 |
|
 ・クラッチケーブルの先端がクラッチペダルより外れたら、クラッチケーブルをエンジンルーム側へ押し込みます。 ・クラッチケーブルの先端がクラッチペダルより外れたら、クラッチケーブルをエンジンルーム側へ押し込みます。
|
|
 【取外完了 / 取外したクラッチケーブルの状態】 【取外完了 / 取外したクラッチケーブルの状態】
・これでクラッチケーブルの取外が完了しました。 |
|
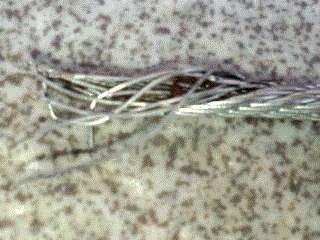 ・取外したクラッチケーブルを確認したところ、ワイヤーがちょうど真ん中ぐらいで切断していました。 ・取外したクラッチケーブルを確認したところ、ワイヤーがちょうど真ん中ぐらいで切断していました。
クラッチケーブルはストレートの取付ではなく、曲げながらクラッチケーブルは固定されているため、多少なりとも負荷はかかっていると思います。
141,000Km走っているので金属疲労で切断または、クラッチが減っていてワイヤーにかかる負荷が多くなったかもしれません。 |
| |
| ■クラッチケーブル取付 |
|
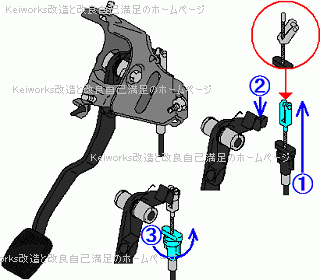 【クラッチペダルにクラッチケーブル取付】 【クラッチペダルにクラッチケーブル取付】
・クラッチペダルの上部にクラッチケーブルの先端を取付します。
作業手順としては左の図のようになります。
この図を見る限りでは簡単そうに見えますが、ここからが一番大変な作業になります。
クラッチペダルブラケットを取外さなくてもできそうですが、クラッチペダルブラケットを取外した方が作業は楽です。
確実にクラッチケーブルの先端が入った事も確認できます。 |
|
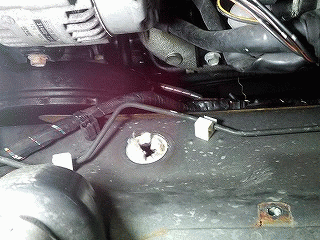 【クラッチケーブル差込】 【クラッチケーブル差込】
・クラッチケーブルをエンジンルーム側より車内に引き込みます。
(左の写真:下側はエンジン) |
|
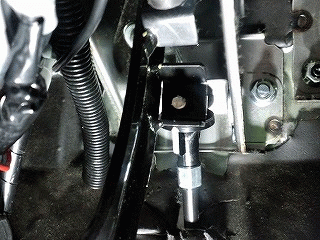 【クラッチケーブル(車内側)固定】 【クラッチケーブル(車内側)固定】
・クラッチペダルの下奥から出ているクラッチケーブルに付いている黒いプラスチックをクラッチペダルブラケットに差し込んで、90°回してクラッチケーブルを固定します。
※左右どちらに回しても同じです。 |
|
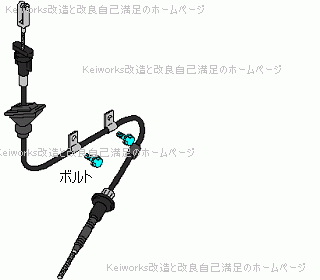 【車体側クラッチケーブル固定ボルト取付】 【車体側クラッチケーブル固定ボルト取付】
・車体側にクラッチケーブルを固定するボルト(2本)を取付します。
どちらも手の入りにくい所にあります。
リフトのある環境ではないので、寝ながらの作業になるため指が攣りそうになります。 |
|
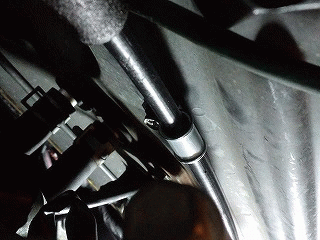 ・助手席側のクラッチケーブルをボルトをラチェットハンドルとソケット[10mm]で固定します。 ・助手席側のクラッチケーブルをボルトをラチェットハンドルとソケット[10mm]で固定します。
(左の写真:左側はエンジン) |
|
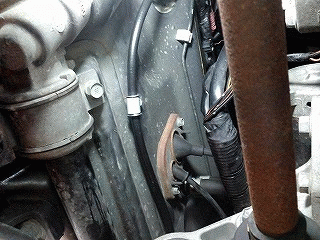 ・運転側のクラッチケーブルをボルトをラチェットハンドルとソケット[10mm]で固定します。 ・運転側のクラッチケーブルをボルトをラチェットハンドルとソケット[10mm]で固定します。
(左の写真:右側はエンジン) |
|
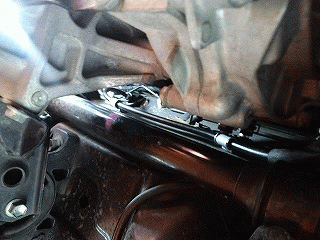 ・クラッチケーブルの車体側の固定ができました。 ・クラッチケーブルの車体側の固定ができました。
(左の写真:上側はエンジン) |
|
 【ゴムカバー取付】 【ゴムカバー取付】
・手で黒いゴムカバーの周りを押しながら車体側に取付けます。
|
|
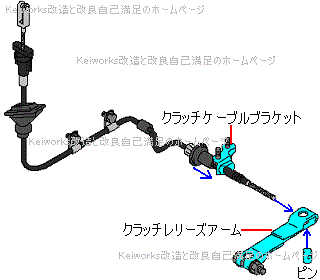 【クラッチケーブルブラケット/クラッチレリーズアーム/ピン取付】 【クラッチケーブルブラケット/クラッチレリーズアーム/ピン取付】
・クラッチケーブルの先端のラバーを外してワイヤーにグリスを塗って元に戻します。
・クラッチケーブルを取外前と同じ経路で引き込みます。 |
|
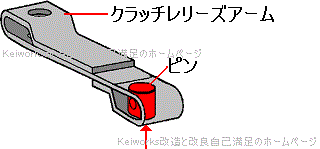 ・ピンにグリスを塗ってからクラッチレリーズアームに取付します。 ・ピンにグリスを塗ってからクラッチレリーズアームに取付します。
ピンの中央に空いている穴の向きに注意してください。 |
|
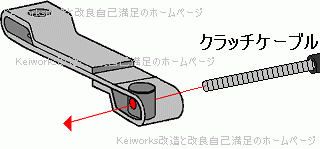 ・クラッチケーブル(エンジン側)の先端をピンの穴へ通します。 ・クラッチケーブル(エンジン側)の先端をピンの穴へ通します。
|
|
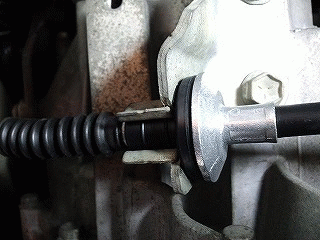 ・クラッチケーブルの太くなっている部分をクラッチケーブルブラケットにスライドして取付けます。 ・クラッチケーブルの太くなっている部分をクラッチケーブルブラケットにスライドして取付けます。
(左の写真:右側がフロントバンパー側) |
|
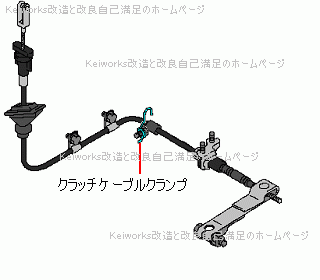 【クラッチケーブルクランプ取付】 【クラッチケーブルクランプ取付】
・クラッチケーブルクランプにクラッチケーブルを取付/固定します。
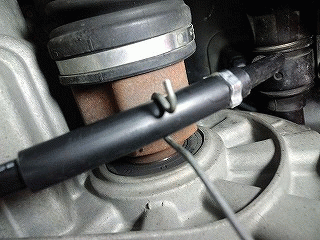 (左の写真:左側はフロントバンパー側) (左の写真:左側はフロントバンパー側)
|
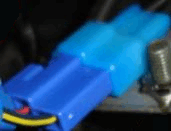 |
【クラッチスタートカプラー(メス)取外】※クラッチペダルブラケットを取外して作業する方だけ
※スターボ、エンジンスタートボタン、リモコンエンジンスターターなど取付で任意で外している人は、次の作業です。
・クラッチペダルブラケット(クラッチペダルASSY)の左側にクラッチスタート(クラッチペダルを踏まないとエンジン始動できない安全装置)の青いカプラーがあります。
・青いカプラー(メス)を外します。
 関連:ターボタイマー取付・クラッチスタートキャンセル 関連:ターボタイマー取付・クラッチスタートキャンセル
→ こちら |
|
 関連:リモコンエンジンスターター取付 関連:リモコンエンジンスターター取付
→ こちら |
|
 関連:HONDA S2000用エンジンスタートスイッチ流用取付 関連:HONDA S2000用エンジンスタートスイッチ流用取付
→ こちら |
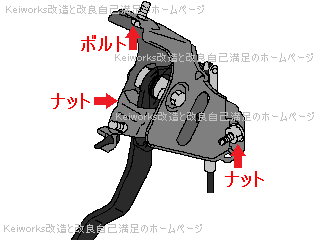 |
【クラッチスタートカプラー(オス)取外】※クラッチペダルブラケットを取外して作業する方だけ
・クラッチペダルブラケットに付いている青いカプラー(オス)をプライヤーでクラッチペダルブラケットから取外します。
【クラッチペダルブラケット取外】※クラッチペダルブラケットを取外して作業する方だけ
※エクステンションバーはできるだけ長い物を使用した方が作業は楽です。
私はハンドルの下に3/8のラチェットハンドルが付くので、ASTRO PRODUCTSで販売している「スピンナハンドル[300mm]」を使用しています。
この工具を使用すると、無理な姿勢はしなくても作業できます。
・クラッチペダルブラケットの上部を固定しているボルト1本を、ラチェットハンドルにエクステンションバー、ソケット[12mm]を取付けてボルト取外します。
・クラッチペダルブラケットの左右を固定しているナット2個を、ラチェットハンドルにエクステンションバー、ソケット[12mm]を取付けてナット取外します。
・クラッチペダルブラケットを少し手前に動かします。
クラッチケーブルが付いたままなので、無理に動かさないでください。
|
 |
【クラッチケーブルの先端取付】※鏡を使用した方が作業は楽です。
・クラッチケーブルの先端は遊びができているため、ワイヤーを持ち上げただけではクラッチペダルに簡単に取付ができません。
 クラッチケーブルの先端を針金に引っかけて、クラッチペダルブラケットの上部に上げます。 クラッチケーブルの先端を針金に引っかけて、クラッチペダルブラケットの上部に上げます。
クラッチケーブルの先端を指で押さえてクラッチペダルの上部の取付位置に引っかけます。
この辺になるとよく見えない状態なので手先の感覚になりますが、クラッチペダルに入るとすぐわかります。 |
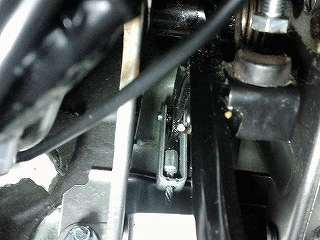 |
・クラッチケーブルの先端がクラッチペダルに取付できると左の写真のようになります。 |
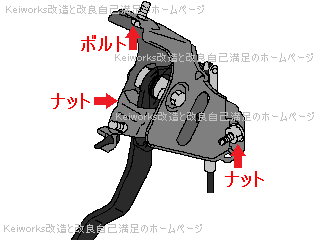 |
【クラッチペダルブラケット取付】※クラッチペダルブラケットを取外して作業した方だけ
・クラッチペダルブラケットの左右を固定しているナット2個を、ラチェットハンドルにエクステンションバー、ソケット[12mm]を取付けて取付します。
・クラッチペダルブラケットの上部を固定しているボルト1本を、ラチェットハンドルにエクステンションバー、ソケット[12mm]を取付けて取付します。 |
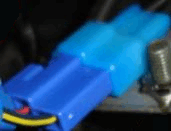 |
【クラッチスタートカプラー(オス)取付】※クラッチペダルブラケットを取外して作業する方だけ
・クラッチペダルブラケット(クラッチペダルASSY)にクラッチスタートの青いカプラー(オス)を取付します。
【クラッチスタートカプラー(メス)取付】※クラッチペダルブラケットを取外して作業した方だけ
・クラッチスタートの青いカプラー(オス)に青いカプラー(メス)を差し込みます。
 関連:ターボタイマー取付・クラッチスタートキャンセル 関連:ターボタイマー取付・クラッチスタートキャンセル
→ こちら |
|
 関連:リモコンエンジンスターター取付 関連:リモコンエンジンスターター取付
→ こちら |
|
 関連:HONDA S2000用エンジンスタートスイッチ流用取付 関連:HONDA S2000用エンジンスタートスイッチ流用取付
→ こちら | |
|
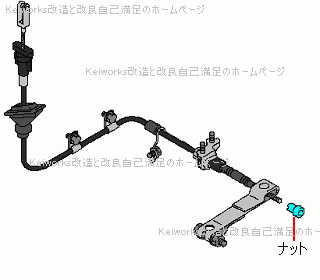 【ナット取付】 【ナット取付】
・ナットをクラッチケーブル(エンジン側)の先端に差し込みます。
このナットの先が湾曲している面をピンに合わせます。

|
|
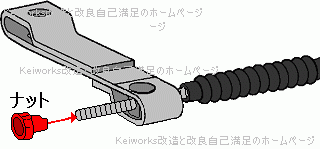 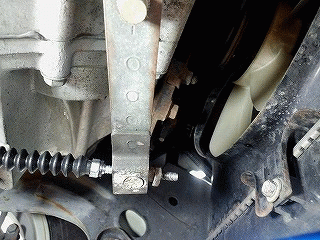 (左の写真:左側はエンジン) (左の写真:左側はエンジン)
|
| |
|
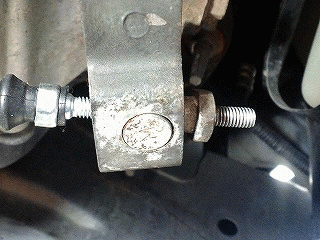 【クラッチケーブル(エンジン側)仮調整】 【クラッチケーブル(エンジン側)仮調整】
・ナット取外前に測った数値を参考に仮で合わせます。
私の車の場合は、ナット取外前は16mmでしたが、14mmを基準に調整しようと思います。
ワイヤー部分をちょっと張りを持たせてナットを回します。
(左の写真:左側はエンジン) |
| |
| ■運転席側シート取付 ※運転席側シートを取外した方だけ |
 |
【運転席シート/センターコンソール取付】
・運転席シートを車内へ取付します。
運転席シートを固定するボルトの穴の位置にシートレールの穴を合わせます。
・運転席シートを固定しているボルト4本を取付します。
タイヤ交換のように対角線にボルトを締め付けします。
均等に締め付けしない場合、歪みができ、異音発生します。 |
 |
・運転席シートレールに、運転席シートを固定しているボルトを隠しているグレーのプラスチックカバーを3つを取付します。
*ドア側(前)のフロントアウトサイドカバー
*センターコンソール側(後)のリヤインサイドライトカバー(左の写真)
*ドア側(後)のリヤアウトサイドカバー
・運転席シート下のカプラー(シートベルト警告灯/シートヒーター[4WDのみ])を差し込みます。 |
 |
・センターコンソールを取付します。
取付方法は下記の関連リンクを見てください。
 関連:センターコンソール脱着方法 関連:センターコンソール脱着方法
→ こちら(取付方法)
【運転席シート調整】
・運転席のシートを自分のベストポジションションにシートを移動してください。 | |
| |
| ■クラッチケーブル調節 |
|
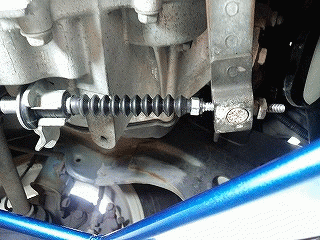 【クラッチケーブル(エンジン側)調整】 【クラッチケーブル(エンジン側)調整】
・この状態でクラッチペダルを数回踏んでみます。
ワイヤーがなじんだところでナットでクラッチケーブルの調整をします。
・調整後、クラッチレリーズアームのガタツキ(ワイヤーの遊び)が無いか確認します。
この時点でもクラッチペダルを踏んだ時の力で踏まなくてもス〜っと踏めます。
今までの状態から劇的に変わりました。
(左の写真:左側はエンジン) |
|
 【クラッチペダルの遊びとクラッチペダルと床板の隙間】 【クラッチペダルの遊びとクラッチペダルと床板の隙間】
・エンジンは始動しないで、車のサイドブレーキがきちんと引かれている事を確認します。
・クラッチペダルを足でゆっくりと(1cm/秒位の速さで)、最初は力を入れずに押してみてください。
・クラッチペダルを押す途中2箇所ほど引っかかる地点(抵抗のある地点)があります。
・クラッチペダルを放した地点から1箇所めの抵抗のある地点までは、クラッチペダルの遊びです。
1箇所めの抵抗のある地点から2箇所めの抵抗のある地点までが、クラッチワイヤーの遊びです。
・クラッチ遊びを調整しても、クラッチディスクが限界まで磨耗している場合は交換となります。
・クラッチ遊びの調整を怠ると、すぐクラッチが滑ります。
半クラッチを多用すると、磨耗が早くなります。
クラッチが限界近くまで磨耗すると、床からペダルをけっこう放さないとクラッチがつながらなくなります。
クラッチを新品に交換すると、床からペダルを少し放しただけでクラッチがつながります。 |
|
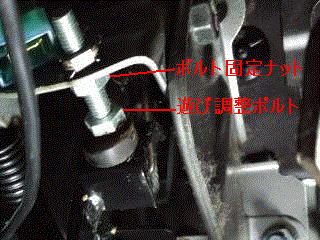 【クラッチペダルの遊び】※Kei取扱説明書のサービスデータより 【クラッチペダルの遊び】※Kei取扱説明書のサービスデータより
・クラッチペダルの遊び調整ボルトは、ナットで絞めて固定されているので、ナットをスパナー[8mm]で緩ませます。
・遊び調整ボルトを手で回してクラッチペダルの遊び(ボルトの上の面とクラッチペダルのゴムの面)を15〜20mmの範囲で調整します。
・遊びの調整が終わったら、ナットをスパナー[8mm]で締めてボルトを固定します。 |
|
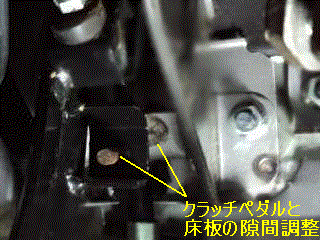 【クラッチペダルと床板の隙間】※Kei取扱説明書のサービスデータより 【クラッチペダルと床板の隙間】※Kei取扱説明書のサービスデータより
・クラッチペダルを奥まで押した時(クラッチが切れた時)に、クラッチペダルと床板の隙間を60mm以上開けて調整します。
通常は弄る所ではありませんが、クッションが付いている所です。
ここにゴムなど入れてクラッチペダルと床の隙間を調整してください。
純正部品を購入する方は下記の部品を手配してください。
ペダル側 → 09321-06026 ※10型
クラッチペダルブランケット側 → 09321-06033 ※10型 |
|
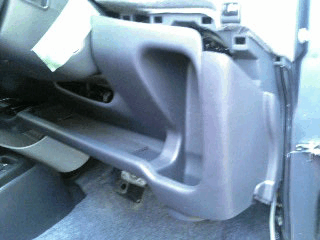 【ペダル関係グリス塗布】 【ペダル関係グリス塗布】
・空調の暖房の風を足元にしていると、グリスが乾燥したり、ゴミが付着している場合があるので、ティッシュペーパーなどで拭き取った後、クラッチ、ブレーキ、アクセルの各ペダルの可動部やワイヤーにグリスを塗ります。
【コンソールアンダートレイ/ダッシュサイドトリム取付】
・コンソールアンダートレイとダッシュサイドトリムを取付します。
コンソールアンダートレイとダッシュサイドトリムの取付方法は、下記の関連リンクを見てください。
 関連:コンソールアンダートレイ/ダッシュサイドトリム脱着方法 関連:コンソールアンダートレイ/ダッシュサイドトリム脱着方法
→ こちら(取付方法) |
|
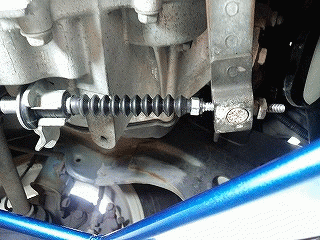 【クラッチケーブル(エンジン側)グリス塗布】 【クラッチケーブル(エンジン側)グリス塗布】
・黒いラバー部分を外してグリスを注入します。
水などの侵入でワイヤーが錆びにくくする事と、ワイヤーの滑りをよくするためでもあります。
(左の写真:左側はエンジン) |
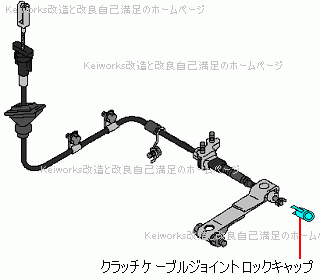
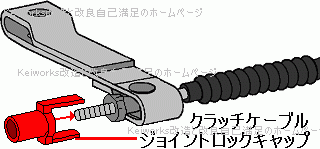 |
【クラッチケーブルジョイントロックキャップ取外】
・クラッチケーブルジョイントロックキャップ」の向きに注意して、クラッチケーブルの先端に差し込み取付します。
 ラジエーター側 ラジエーター側
|
|
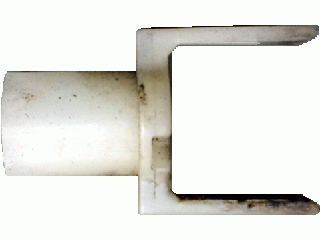 クラッチケーブル側 クラッチケーブル側
|
 |
【ジャッキダウン】
・フロント側を3t(2t)ジャッキで車体を持ち上げます。
・左右の前輪タイヤの下にあるコンクリートブロックを取外します。 ※リジットラックの代替品
・車体をゆっくりおろします。
・リアタイヤの後側にタイヤ止めを取外します。
【作業完了】
・作業完了です。
【動作確認】
・クラッチペダルを踏んだ状態でエンジン始動させて、クラッチのつながりを確認します。
・ギヤをニュートラルにして車が進まない事を確認します。
・1週間ぐらい経ってからクラッチケーブルの状態をもう一度確認して、調整が必要であれば調整してください。 | |
| |
| ★施工後 |
|
・クラッチケーブルの交換は約180分でした。 ※写真、メモする時間含む
SUZUKIの標準作業時間では0.7(約40分)ですが、リフトなど設備が整っている所での話です。
体や手が入りにくく狭い所の作業だったので、こんなもんだと思います。
作業していて一番大変だったのが、クラッチペダルにクラッチケーブルの先端を取付する事でした。
作業で一番時間がかかって、初めからクラッチペダルブラケットを取外して作業していれば、1時間早く終わっていたと思います。
軽自動車でクラッチケーブルの交換は、無理な姿勢をして交換作業をしていたため体のあちこちに痛みを伴います。
近くの整備工場の方と修理の話をした時に、あまりやりたがらない表情をしていたので、今回の作業をして納得しました。
でも、141,100Kmまでワイヤーが切れず乗れたのもすごい事だと思います。
・1/1〜1/6の6日間はmera e:sで過ごしていました。
Keiworksのようにアクセルを踏んでも加速しない。
アイドルストップするので、キャンセルしない限り車が止まるたびにエンストする。(特に交差点の右折時は正直怖いです。)
何でもない所でスマートアシストが勝手に働くので、キャンセルしないと乗っていられない。
など、何となく運転するのに疲れました。
自分の車が一番です。
あれだけ車は信号を出していましたが、早めにクラッチケーブルを交換していればよかったです。
年末でいろいろ条件が悪そうな感じではありましたが、12/31の夕方に整備工場が捕まってよかったし、これが初詣などで出かけていて農道のど真ん中で止まったなんて考えると、かなりラッキーだったと思えます。
・写真と図が多かったので、ページ作成がいつもより時間がかかりました。
|
●私の車のクラッチケーブルが切れた時の状況
・クラッチケーブルが切れたのは、2016年12月31日の大晦日の16:50頃でした。
周りは暗くなっていて、県道を走行中で自宅から5Km離れたの所でした。
クラッチケーブルが切断した時はスピードも出ていなくて、踏切で数台止まっていたため、止まる直前にクラッチペダルを踏んでギヤをニュートラルにしたところで「バツ」と大きな音と同時に左足に一瞬振動があったため、クラッチワイヤーが切れた事がすぐに判りました。
ちょうど数m先に車1台置ける幅の所があったので、惰性で入って車を停止しました。
道路の真中で停車せず事故を起こさずに車を安全な場所に停められたので良かったです。
これが自宅からかなり離れた所、天候不良、夜間、交通量の多い幹線道路、またバイパスでスピードが出ている時でなくて良かったです。
車を停車中にクラッチペダルを踏んでもいつもの感覚はありませんでした。
この時、エンジンの回転を合わせてギヤを強引につないで走行したくなかったので、業者に依頼するしか選択方法がありませんでした。
私の携帯電話には万が一のトラブルに対処するために自動車関連の電話番号をいくつか登録していました。
車の引き取りができる所に電話しようと思ったのですが、大晦日の夕方でディーラーは当然年末年始の休みに入っています。
断られるの前提で自宅近くの自動車整備工場に電話したら、営業は終わっていましたが自宅までレッカーしてくれると言ってくれたので助かりました。
レッカーする時はロープが常に張った状態を保ち、レッカーする車のブレーキランプと曲がる時に注意をしていれば問題ありません。
牽引されている時の路面は乾いた路面でしたが、この時期にしては雪や圧雪、凍結も無く助かりました。
そう考えるといろいろな条件も重なり非常にラッキーだったかもしれません。 → 年明けて停まったら最悪でした。
レッカーしてくれた整備士の方に修理を依頼しようと思って話をしていると、部品が届くのに時間がかかるとの事で、自分で部品を手配して修理した方が早そうだったので、レッカー代だけ払いました。
「クラッチケーブルを自分で交換できない場合は、私の会社(整備工場)に連絡ください。」と整備士の方が言っていました。
この時期は天候が悪いことが多く、私のガレージには屋根がないため天候を見て修理する事になります。
次の日(元旦)の午前中に小雨が降っていましたが、部品が来る前に切断したクラッチケーブルを取外しました。
年明けは車を使う事ができなくて何かと不便でしたが、1月4日から仕事なのでmira e:sで3日間は会社に出勤しました。 | |
| |
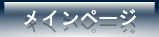 Copyright(C) ty_plus5638 All Rights Reserved. Copyright(C) ty_plus5638 All Rights Reserved. |

